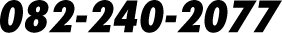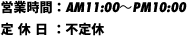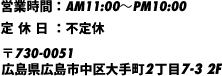カテゴリ
月別 アーカイブ
- 2024年5月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (3)
- 2023年9月 (6)
- 2023年8月 (8)
- 2023年7月 (7)
- 2023年1月 (1)
- 2022年11月 (1)
- 2022年10月 (1)
- 2022年9月 (2)
- 2022年7月 (6)
- 2022年6月 (3)
- 2022年5月 (4)
- 2022年3月 (5)
- 2022年2月 (6)
- 2022年1月 (4)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (4)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年5月 (1)
- 2021年4月 (1)
- 2021年3月 (4)
- 2021年1月 (2)
- 2020年11月 (1)
- 2020年10月 (1)
- 2020年8月 (2)
- 2020年4月 (3)
- 2020年3月 (1)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (3)
- 2019年12月 (7)
- 2019年11月 (2)
- 2019年10月 (3)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (6)
- 2019年7月 (16)
- 2019年6月 (21)
- 2019年5月 (22)
- 2019年4月 (7)
- 2019年3月 (3)
- 2019年2月 (7)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (6)
- 2018年11月 (8)
- 2018年10月 (3)
- 2018年9月 (12)
- 2018年8月 (6)
- 2018年7月 (3)
- 2018年6月 (8)
- 2018年5月 (10)
- 2018年4月 (3)
- 2018年3月 (2)
- 2018年2月 (1)
- 2018年1月 (3)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (4)
- 2017年10月 (2)
- 2017年9月 (4)
- 2017年8月 (5)
- 2017年7月 (1)
- 2017年3月 (1)
最近のエントリー
ブログ 4ページ目
臀筋:解剖学編
臀筋もまた頻出単語ですね。百聞は一見に如かず。毎回恒例、画像で確認していきましょう!

臀筋とは、【大・中・小の臀筋】と【大腿筋膜張筋】、これら4つの筋肉の総称です。
大臀筋は大腿四頭筋(=太もも前側)に続き2番目に大きいんですよ。
代謝アップ、ダイエット目的にお尻を鍛える理由はここにあるんですね。
大・中・小臀筋これら3つの筋肉は層になっています。
ところで。
 ぴょこっと飛びでてるこの○の部分気になりませんでしたか?
ぴょこっと飛びでてるこの○の部分気になりませんでしたか?この○部分は大臀筋の停止部です。
『停止部?いや、待て待て。付着と言いつつ浮いてるじゃん!』って思った方、、、
最高です。(笑)
大臀筋は大腿骨の臀筋粗面(大腿骨のザラザラした部分)と【腸脛靱帯】という靭帯に付着していて、
この浮いてる部分はその腸脛靱帯に付着します。
では、腸脛靱帯とは何か。
ここで出てくるのが大腿筋膜張筋。
(先程の画像よくよく見たら大腿筋膜張筋がないことにお気づき頂けたでしょうか?)
この腸脛靱帯、実は大腿筋膜張筋から移行して腸脛靭帯になってるおもしろ靭帯なのです。
図で見るとこんな感じ。
 青い部分が大腿筋膜張筋でその下が腸脛靭帯です。
青い部分が大腿筋膜張筋でその下が腸脛靭帯です。大臀筋、もといお尻は太ももの横まであるんですね。
それでは起始停止作用について!
【大臀筋】
起始:腸骨、仙骨・尾骨
停止:(大腿筋膜張筋、)腸脛靭帯、大腿骨の臀筋粗面
作用:股関節伸展、外旋、膝関節伸展
【中臀筋】
起始:腸骨稜
停止:大腿骨の大転子
作用:股関節外転、内旋(前部)、外旋(後部)
【小臀筋】
起始:腸骨外側
停止:大腿骨の大転子
作用:股関節外転、僅かな内旋
【大腿筋膜張筋】
起始:上前腸骨棘
停止: 腸脛靭帯を経て、脛骨外側顆
作用:股関節外転、内旋、屈曲、膝関節伸展
※作用について
股関節伸展=足を後ろに引く
股関節外転=足を外側に開く
股関節外旋=足を外回しする
 起始停止を確認する理由。それはストレッチ、トレーニングの質を高めるためでしたね。
起始停止を確認する理由。それはストレッチ、トレーニングの質を高めるためでしたね。細かい名前(例:臀筋粗面)なんてぶっちゃけいいんです。
重要なのはどの辺りにどんな風に付着しているか。
とはいえ。腸骨ってどこぞ。そんな方いらっしゃるのではないでしょうか。
ざっくりと骨盤、でもまあ、確かに間違いないのですが!
皆さんには是非とももう少しだけ細かく覚えて欲しい!
ということで、骨盤について!
いやあ、今回の解剖学編、なかなか濃いですよ~(笑)
骨盤とは3つの骨(寛骨・仙骨・尾骨)で構成されており、
また寛骨はさらに腸骨・坐骨・恥骨が癒合したものなんです。

ほうほう。これで皆さん骨盤の解像度が上がったのではないでしょうか!
大体このあたり~っていうのがわかればOKなんですが!それでもやっぱり細かい場所が知りたいって方のために!

〇部分が臀筋の起始部だったり停止部だったりします。
(臀筋粗面以外の3つは簡単に触診できますよ)
さて、これで骨盤の解剖学は完璧ですね!
骨盤がわかれば、お尻の筋肉の付着部分もわかります!
今回の投稿で臀筋が3層になってることや、太もも横まで付いてると知った方、ラッキーです!
大きい筋は力を発揮しやすいですが、小さい筋は意識しないと衰えていく一方。
漠然とお尻~ではなく、この下に中小臀筋もいる、ここまで付いてるってイメージするだけで、ずいぶん質が変わってきますよ!
次回、ストレッチ編、そしてトレーニング編に続きます!
(HIROSHIMAストレッチ)
2022年9月16日 11:02





四十肩、五十肩ってなに?~実技編~
どうも、楠本です。
前回の続きです。今日は五十肩の痛みがある程度落ち着いてきた時に、自分でできるストレッチと言うか運動というか...、ケアの方法をお伝えします。
まず、注意点としては肩の痛みが筋肉の断裂、石灰が溜まって炎症が起きているやつでないかきちんと整形外科で診てもらってください。
MRIや超音波で確認してもらうのがベストです。筋肉の断裂、石灰沈着によるものではないとの診断を受けた方のみ実践してください。
この痛みはやっていいの?開始のタイミングが分からないという方はHIROSHIMAストレッチにご来店いただき、ご相談ください。
それではセルフケアの方法をお伝えします。
今からお伝えする方法は立って行います。
*写真は右肩が五十肩のパターンで撮影してます!
まず、左手の指先を鎖骨の下に置いておきます。
(この指は胸の筋肉の収縮が起こってしまってるか確認用です。)
 右肩はやや後ろに引いておきます。
右肩はやや後ろに引いておきます。(横から見るとかこんな感じ。角度的には約5~10°ぐらい、お尻に触れるぐらいのイメージです。)

この状態で『腕を内側に捻ります。』
この時大事なのが肩が前に出ないこと、右胸の筋肉が収縮しないようにすることです!
痛みが出ない最大限内側に捻ったら、そこで3秒キープ。
そして元に戻します。

これを繰り返します。回数としては10回を目安でいいかと思います。
きちんと出来てる場合は右わきが疲れてくる感覚があります!
一回でスパッとよくなる訳ではありませんが、続けていくと動かしたときの肩の外から後ろが突っ張る感じが抜けていきます。
毎日根気よく継続してください。
ただ、無理は禁物です。痛みが強く出すぎない範囲で行ってください。
うーん、いまいちこれで合ってるかわからんって方は一度、ご来店ください。しっかりチェック、指導させて頂きます。
では、今回はここまで!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
(HIROSHIMAストレッチ)
2022年7月31日 12:20





四十肩、五十肩ってなに?
どうも、楠本です。
今日は皆さんもよく耳にする『四十肩、五十肩』について書いてみます。
医学用語では『肩関節周囲炎』という疾患の中に含まれています。
文字通り肩関節周辺の炎症が起こる疾患ですよー!ということです。
ざっくりとした名前ですよね(笑)
周囲炎というぐらいですから、色んな肩の状態が含まれています。
どういうことかと言いますと、
筋肉や滑液包(緩衝材のようなクッションみたいなもの)に炎症が起こるもの、
筋肉内に石灰が溜まって激しい炎症が起こり、たまに骨化してしまうもの、
筋肉の断裂が起こってしまうものなどなど
色んな状態を含んで肩関節周囲炎と言ってますということです。
その中でも『四十肩、五十肩』というものは
『原因不明で、なんか加齢とともに筋肉や滑液包や靭帯などが脆くなったり、硬くなったり色んな変化が起こって炎症が起きてしまうもので、1~1年半で自然に元の状態近くまで戻るもの』
を指してます。
なので、石灰が溜まるものとか筋肉が切れてしまうものは肩関節周囲炎に含まれてはいるんですが、五十肩とか四十肩とは違います。
そして、筋肉が切れたり、石灰が溜まったりするものはきちんと整形外科で診てもらったほうが、後々困ったことになりにくいです。
話が脱線しました…。
四十肩、五十肩になると炎症により肩関節が痛みます。そして動かすのが辛くなります。
特に結髪動作(髪を洗うような肩腕の動作)、
 結帯動作(手を下から背中に回す動作、女性だと下着をつける時に必要な動作)
結帯動作(手を下から背中に回す動作、女性だと下着をつける時に必要な動作) が制限されることが多くなります。困りますよね…。
が制限されることが多くなります。困りますよね…。痛みは何ヵ月という長いスパンかけて徐々に消失してきますが、可動域制限はそれ以降も続く事が多くて、痛みや可動域制限が日常生活に問題なくなるまで1~2年ほどかかる。
という流れで治ってきます。
痛みがある程度落ち着いた頃から運動などを行ってなるべく可動域制限がよりよく改善出来るようにすることが大事です。
HIROSHIMAストレッチにおいても五十肩のストレッチ、運動法を提供しています。
もし、お困りの方がいらっしゃったらご相談ください!
次回は自分で出来る五十肩に対するストレッチをご紹介します。
今回はこの辺で♪
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!
(HIROSHIMAストレッチ)
2022年7月30日 12:44





楽にランニングするための○○~実技編~
どうも、楠本です。
今日は前回に引き続き、ゴルフボールによる足裏のケア実技編をお送りします。
足裏は衝撃吸収と足を固めることにより(剛性を高めるといいます)地面からの反発力を上手く推進力にかえる機能が備わっています。
これらがランニングの際に繰り返されることにより、足裏の筋肉や腱膜が疲労し、うまく機能しなくなると足関節、膝関節、股関節などにも障害を生む可能性が出てきます。
なので、特にランニング後は足裏のケアが大事になります。
今回はゴルフボールを使ったセルフケアの方法をお伝えします!
まず、ゴルフボールを床に置いて足で踏んづけます。
足で踏んづけた状態で足を動かしてゴルフボールを転がします。
 転がす場所と方向は以下の写真の通りです。
転がす場所と方向は以下の写真の通りです。内側縦アーチは土踏まずにあたりますので何となくイメージが湧くと思います。
縦方向に足裏でゴルフボールを転がしてみましょう!

外側縦アーチは小指側です。土踏まず程、凹んでいるわけではありませんがここも立派なアーチ機構として働いてますのでケアをしてあげましょう♪

もう1つ、横アーチ。ここもあまり意識されませんがアーチがあります。足に体重がかかった時にべちゃっと潰れ過ぎないようにしています!
ここのアーチが機能しないと靴が窮屈に感じたり、外反母趾の要因の一つではないかなんて言われています。横にゴルフボールを転がしましょう。

各アーチを1分間ずつ、合計3分間ゴルフボールでケアしてみましょう!
何度も言いますが、痛気持ち良い程度に圧力をかけて転がします。痛すぎると筋肉や筋膜、腱膜などを痛める可能性がありますし、カラダに力が入りすぎて上手く緩まない事がありますので、要注意です!
こんな感じで私自身もランニング後にケアをしていますので参考にしてみてください!
それではまたー!
(HIROSHIMAストレッチ)
2022年7月30日 12:42





あっという間の7年間
振り返ればあっという間でもう7年も経ったのかというのが正直なところです。
もっと技術を研鑽し、心を成長させて、来て下さる方々が心身ともに元気になり、
力みの無い穏やかな身体の状態が獲得できるようにスタッフ一同努力していきます。
その為にもまずスタッフ一人一人が力みの無い心身作りを励み、
その感覚を提供できるようにしていきたいと思います。
まだまだ足りない部分はありますが、これからもHIROSHIMAストレッチをよろしくお願いいたします。
スタッフ一同
2022/07/20
(HIROSHIMAストレッチ)
2022年7月20日 11:34





お盆休みのお知らせ
8月16日(火)からは通常通り営業致しますので、皆様の御来店心よりお待ちしております。

(HIROSHIMAストレッチ)
2022年7月18日 13:10





楽にランニングするための○○♪
どうも、楠本です。
ずいぶん前からですが、空前のランニングブームでHIROSHIMAストレッチでもランニングを趣味でされている方のケアを沢山させて頂いております!
自分自身も皆様のように頻度は多くないですが、週1日はランニングして身体全体の調和を図るようにしています♪
今回は楽にランニングするためのケアを一つご紹介します。
結論からお伝えすると『ゴルフボールを使って足裏をケアしましょう♪』ということです。
ゴルフボールでなくてもフォームローラーとか筋膜リリース用の道具でも何でもいいんですが、ゴルフボールが特に使いやすいと個人的に思っています。
なぜ足裏なのかと言いますと、
足裏には下の写真のように3つのアーチ構造があります!馴染みがあるのは内側縦アーチ(青)、いわゆる土踏まずってやつですね。

これらは衝撃吸収の為、また地面からの反発力を上手く身体の推進力に変えるために必要な構造なんです。
ランニングの時には足が地面に着くたびに荷重がかかります。その時の衝撃を吸収しています。
衝撃吸収後は足が硬くなり(良い意味で)、地面からの反発力を上手く利用して前に身体を運んでいきます。
足裏に絞ってランニングについて考えてみると上記の事が繰り返されているわけです。
そうすると足裏の筋肉や腱膜とよばれる組織が疲労してうまく働かなくなります。
更に足裏の筋膜はふくらはぎや太もも裏、お尻、腰~首、頭まで機能的に繋がっていると考えられています。
つまり、足裏のケアは局所にとどまらず、腰痛や太もも裏の張り感などを解消することにも繋がります。
次回は実際のやり方について書いていきます。
運動後のケアもケガの予防に必要ですので、セルフケアも怠らずにするようにしましょう♪
セルフケアが難しい場合はHIROSHIMAストレッチでケアをしましょう!
それではまた!
(HIROSHIMAストレッチ)
2022年7月 8日 16:06





腸腰筋:トレーニング編
使える腸腰筋にする為には、柔軟性はもちろん、しっかり動いてくれる筋肉である必要があります。
ストレッチだけでも、トレーニングだけでもダメです。
それでは腸腰筋ちゃんを動かしていきましょう!の前に、ひとつ覚えててくださいな。
【腸腰筋は股関節を90度以上屈曲する際】に主に働きます。
それを踏まえていきますよ~!
トレーニング(1)
1)仰向けで寝て、骨盤後傾位(=床と腰骨の間に空間ができないように)で準備。
足の幅は骨盤幅に開きます。
2)骨盤が揺れないように、足をあげ、しっかり股関節を引き込む
3)おろす
4)反対の足をあげる ×10回(左右各5回ずつ) 2セット
※常に骨盤は後傾位をキープでトレーニング。これは腰を痛めない為の大切な決まり事!

みなさん、今一度確認。やりたいことは?腸腰筋のトレーニング。腸腰筋の作用は?股関節屈曲。
ここで先程のポイント。股関節90度以上屈曲で腸腰筋は作用するんでしたね。
股関節をしっかり引き込んでください。付け根あたりがじんわり熱くなれば正解です。
【更に負荷をかけたい人】
レベル1)おろすのと反対側の足をあげるのを同時に行う ×10回 2セット
レベル2)膝を伸ばしてまず片足10回
レベル3)膝伸ばしてレベル1のこと ×10回 2セット

太腿の裏(ハムストリング)の柔軟性には個人差があります。少し膝を伸ばすだけだもOK。
わたしもハムは硬いので、レベル3がまだまだ課題です。
トレーニング(2)…立ちトレーニング
1)足を90度以上上げておろすの繰り返し…おろすときに足が内外に向けて(画像参照)
※屈曲位で腸腰筋は働くので、足を上げるのが勢いにならないように!
自分の意志でしっかり上げる!
×10回 2セット

ちなみにこの立ちトレ、軸足(動かしてない足)のお尻ももれなく鍛えられます。
グラグラしないように、しっかり地面に突き刺す!
簡単だけど、地味にキツい!お試しあれです。やり方がいまいち分からなければ、お尋ねくださいませ。
(HIROSHIMAストレッチ)
2022年6月 8日 13:35





腸腰筋:ストレッチ編
以前に教わったよって方もいらっしゃるかも?
今一度確認、あーんど!少し負荷を加えるやり方も紹介してるので、チャレンジしてみてください!
付け根が伸びる感じがしたら正解です!
ストレッチ(1)
1)膝立ちの状態から一方の足を前に出す
2)そこから前の足にしっかり体重をかけていく
=伸ばしてる側(後ろの足)の付け根が伸びてる感じがしたらOK
※足がしっかり外旋してると股関節の詰まり感が少ないかも!“膝と爪先”がしっかり“外”を向くように前足をついてみてください。

【更に負荷をかけたい人】
レベル1)最初の一歩を遠くに出す
レベル2)前側についてる膝がしっかり曲がるポジションから伸ばしてる側と反対の手で足を掴む…お尻と踵が付いたら最高!
レベル3)レベル2の状態から肘をつけ上体を倒す
→腸腰筋のスタートは鳩尾!起始部を遠ざけることで更に伸びます。

ストレッチ(2)
1)膝立ちスタートで、両方の踵を付け、膝を少し開く
2)※骨盤を前に押し出し片方の手を上にあげる(※壁に骨盤をくっ付けるイメージ)
3)この骨盤をキープしたまま、反対側の手は踵(負荷をかけたい人はお尻の近く)に置き、そのまま斜め後ろ横に倒れる
※伸ばしたいのはあくまで付け根!脇腹が伸びる感覚がある人は置く手の位置や、倒す方向を少し調整してください。

ポイントは骨盤を壁にくっ付ける(=骨盤を前に押し出す)こと!伸ばしたいのは、腸腰筋です!
痛すぎず、伸びてるなあって感じるところ、痛気持ちいいと感じるところでストレッチしてくださいね!
(HIROSHIMAストレッチ)
2022年6月 6日 14:11





腸腰筋:解剖学編
今回は、改めて腸腰筋についてご紹介。
まず腸腰筋とは、上半身と下半身を結ぶ筋肉です。正しい姿勢を保持する上でポイントとなる筋肉になります。(猫背改善の為、色々試しているのになかなか改善されないって方。上半身だけにフォーカスしていませんか?もしかしたら猫背の原因は腸腰筋にあるかもしれませんよ。)

腸腰筋は、"腸"骨筋と大"腰"筋(小腰筋)、2つを合わせた筋肉のことをいいます。
起始部:背骨(骨盤)~停止部:大腿骨の小転子
作用:股関節屈曲
 筋肉は起始部と停止部が近付くと収縮(=作用)します。つまり、座っているときに腸腰筋は収縮(=作用)しています。また同じ姿勢が続くことで、筋肉は固まってしまうので、長時間座り仕事が続いている方は特に固まりやすいんです。腸腰筋が硬いと、反り腰や腰痛、猫背の原因になります。
筋肉は起始部と停止部が近付くと収縮(=作用)します。つまり、座っているときに腸腰筋は収縮(=作用)しています。また同じ姿勢が続くことで、筋肉は固まってしまうので、長時間座り仕事が続いている方は特に固まりやすいんです。腸腰筋が硬いと、反り腰や腰痛、猫背の原因になります。固まってるというのは、筋肉が縮んで硬くなった状態で、伸びもしなければ、これ以上縮まることもできない状態。猫背や腰痛を改善したくば、伸び縮みがキチンとできる、使える腸腰筋にする必要があるのです!ご飯を食べたら歯を磨くように、使った筋肉は伸ばして鍛えるのです!
ということで、次回から、腸腰筋のストレッチ、トレーニングについてご紹介します。
(HIROSHIMAストレッチ)
2022年6月 3日 11:55





<<前のページへ|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|次のページへ>>
100件以降の記事はアーカイブからご覧いただけます。