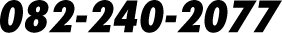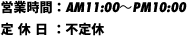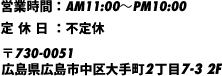カテゴリ
月別 アーカイブ
- 2024年5月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (3)
- 2023年9月 (6)
- 2023年8月 (8)
- 2023年7月 (7)
- 2023年1月 (1)
- 2022年11月 (1)
- 2022年10月 (1)
- 2022年9月 (2)
- 2022年7月 (6)
- 2022年6月 (3)
- 2022年5月 (4)
- 2022年3月 (5)
- 2022年2月 (6)
- 2022年1月 (4)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (4)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年5月 (1)
- 2021年4月 (1)
- 2021年3月 (4)
- 2021年1月 (2)
- 2020年11月 (1)
- 2020年10月 (1)
- 2020年8月 (2)
- 2020年4月 (3)
- 2020年3月 (1)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (3)
- 2019年12月 (7)
- 2019年11月 (2)
- 2019年10月 (3)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (6)
- 2019年7月 (16)
- 2019年6月 (21)
- 2019年5月 (22)
- 2019年4月 (7)
- 2019年3月 (3)
- 2019年2月 (7)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (6)
- 2018年11月 (8)
- 2018年10月 (3)
- 2018年9月 (12)
- 2018年8月 (6)
- 2018年7月 (3)
- 2018年6月 (8)
- 2018年5月 (10)
- 2018年4月 (3)
- 2018年3月 (2)
- 2018年2月 (1)
- 2018年1月 (3)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (4)
- 2017年10月 (2)
- 2017年9月 (4)
- 2017年8月 (5)
- 2017年7月 (1)
- 2017年3月 (1)
最近のエントリー
ブログ 3ページ目
陰陽シリーズ~集中と執着~
自分でもなぜこの題材を選んだのか?もっと言えばこの陰陽の説明、、ブログを再開したのが陰と陽だったので流れで陰陽シリーズになってしまったのですが、ブログ見る限りでは完全に変な人ですよね。
安心してください、実際はもっと変です(笑) ということで今日はかなり難しい所にツッコんでいきます。
持続的集中は前回お話しさせて頂いた、強い愛で発動する真ん中【サットバ】でした。(まっすぐ一直線のイメージ)
執着も実はとても似ているんです。強い愛なのは間違いないのですが、真っ直ぐではありません。歪んでいてエネルギーが通り切らず、ところどころにうっ滞しています。
集中と執着の違いとして身体で現れるのは無意識の力みです。執着の場合はこの無意識の力みが出やすく、その原因としては真ん中を使えていないから、もっとツッコんでいうと【自己都合の愛】のため純粋な真ん中を使えず、どこか歪んだ形として使う結果が無意識の力みとなって現れます。かといって無意識の力み全てが執着というわけではありません。ですが基本的に無意識の力みは本来の使い方とは違った使い方によって出てきます。執着の他にも、拒絶、不快、反感、などがあります。
まとめてみると、持続的集中は真っ直ぐな強い愛であり、執着は歪みのある自己都合な強い愛ということになります。とはいえ、人類全体をみてこの持続的集中の強い愛をし続けている人はどれくらいいるのでしょうか?過去の聖人、偉人、ブッタ、キリスト、ガンジー、聖母マリア様。 普通の人間には遠く及ばない境地ですが、それでも生きている限り目指すべき場所なのかなと思います。それは修行、苦行的に目指すというよりは(生きることが修行のようなものなので)人生を楽しんで、どんな状況であろうが、心から笑顔でいられる自分になっていけたら良いなと個人的には思います。
辛さも一緒に楽しめる、そんな人生は最高ですね。ではまた。
(HIROSHIMAストレッチ)
2023年7月25日 16:50





陰陽シリーズ~趣味について考察~
趣味こそ無限大にあるんじゃないかと思うくらい、個人個人で全然違いますよね。
スポーツ、読書、寝ること、お風呂、人間観察、テレビ、ゲーム、コレクター、などなど。
陰陽目線からみると趣味の目的は大きく2つです。
一つ目は前回の嗜好品と同様【陰(愛)の消化】です。陰と向かい合えるように踊らされないように趣味によって楽しく愛を消化し明朗となり向き合いに備えるということ。
二つ目は【持続的な集中】です。嗜好品は一時的なものであり持続集中の要素はありませんが趣味の場合はこの持続的集中が入っくることが多いです。そして集中はめちゃくちゃ大事です。
【集中】は陰なのか?陽なのか?答えはどちらでもなく中道です。ヨーガの言葉を借りるならラジャスが【陰】、タマスが【陽】、サットバがこの【真ん中、集中】となります。なので陰陽の間が集中です。
好きな物事には集中できる。そこには愛があるから持続的に集中できる。そこに自信【強さ】があればより高いレベルで持続的に集中できるということですね。陰と陽の両方の良い所を取り出した結果が強い愛であり、持続的な高いレベルでの集中という形になります。
なので趣味に没頭している時間はある意味瞑想のような状態に近いですね。
趣味が仕事になる、好きな事を仕事にする良さはこういうポイントにあるのかなと思います。うまくいかない事を、難しいことを含めていても、愛があればその困難は乗り越えるためにあるものだと考えることでしょう。そしてより強さを得て更に高い集中力で目の前に愛を注げます。
集中と似ているのですが、執着というものもあります。次回は執着について考察していきたいと思います。
(HIROSHIMAストレッチ)
2023年7月25日 16:50





嗜好品の役割を考える、、、【陰陽目線】
嗜好品と聞くと何を思い浮かべるでしょうか?
お酒、コーヒー、お菓子、タバコ(最近はタバコは嗜好品とは言わないようです。)などなどあると思います。
生きていく上で絶対必要ではないが、日々の楽しみであり、ストレス発散にもなる、ひと時の癒しを得ることができる、そんな役割を持つのが嗜好品ではないかと思います。
陰陽の目線から考えると嗜好品の役割は【陰(愛)の消化】にあたります。前回お話ししたように愛の形は無限大です。好き、嫌い、憎しみ、執着、色んな形があります。なので陰が膨れ上がると自我(陽)では対処しきれなくなってきます。なので嗜好品によって愛【陰】を消化して自我【陽】を安定させるという選択をとります。
前回も書きましたが強さと優しさの優先順位はまず、強さを鍛えることが大事です。
本当の意味で自己に対して明朗であり強くなれば、そのうち嗜好品に頼ることは無くなって、愛【陰】をうまく理解し照らす方向がわかるようになってきます。
ということは逆に嗜好品は【今の時代は必要不可欠】と言えるかもしれません。死ぬことはなくても、生きづらいこの時代、嗜好品はある意味ありがたい存在です。自己が明朗となるまでは嗜好品の力を借りる。しかし明朗になるごとに、強くなるごとに、その量を減らしたり、断ったりすることが求められます。依存してしまうということは本末転倒でありそれは弱い道です。
嗜好品とうまく向き合い、自己を鍛えて成長していきましょう。
嗜好品と似た形で 【趣味】があります。次回は趣味についての陰陽考察をしてみたいと思います。
それではまた。
(HIROSHIMAストレッチ)
2023年7月25日 16:50





陰について【優しさと激昂の関係性】
前回は陽【強さ、怠惰】だったので今回は陰の優しさと激昂について考えていきたいと思います。
陰サイドをもう一度おさらいしておくと
陰…右、太陽、女性性、優しさ、厳格性、二元性の愛、激昂、
などなどがあります。
強さの極致が【無】なのに対して、優しさ(愛)は【無限大】です。 愛は無限なので色々な形の愛があります。好きも愛、嫌いも愛、愛してるの愛、憎しみも愛、嫉妬も愛、執着も愛、全てひっくるめて愛です。
陰サイドの優しさ(愛)は色んな形がありすぎて自分自身が混乱してしまうのが欠点です。常に正解を求めて探し続けている感じです、これが正解だ!と思ったのに場面が変われば正解も変わり、結局無限大∞の中に放り込まれて、支えや拠り所をまた探しているといった感じです。
なのでこの優しさが弱ってしまうと、拠り所としての厳格性が現れてきます。簡単にいうと法やルールなどが拠り所となってしまいます。法やルールが悪いわけではなく、万人を想う、その結果としてそこに偏りができてしまい、法に則って怒り、ルールを重んじて憎んでしまうという、渦に巻き込まれるわけです。
なので前回話した、強さだけの自己中な愛のない人には、この厳格性を持って対処します。ここに激昂が含まれます。(もう一つの激昂の見方としては単純に太陽のチャクラの通りが悪いため激昂となるという見方)
自己の強さが見つからず、愛だけの場合は無限の形の愛の中、思考の中で行ったり来たりを繰り返す形になりがちです。
なので陰陽両方見てきましたが、両方必要なのです。強いだけではだめだし、優しいだけでも自分自身をを路頭に迷わせてしまう。両方必要なのですが、実は優先順位があります。強さと優しさどちらを先に持つべきなのか、仏教、道教、聖書、バガヴァッド・ギーターいろんな聖典に書かれていますが、自己を明朗にさせる事(強さ)そしてその上に愛(優しさ)を築くことです。
強くて優しい人が最強ということですね。そんな人になりたいものです。ではまた。
(HIROSHIMAストレッチ)
2023年7月16日 16:24





陽について 【強さと怠惰の関係性】
前回に引き続き陰陽についての考察、今日は特に陽の強さと怠惰の関係性についてです。
もう一度陽サイドの特徴を見ておくと、
陽サイド …左、夏【動】、月、猫、男、強さ、弱さ【我】、怠惰、無
などになります。 強さと怠惰の関係性で一番わかりやすいのは百獣の王ライオンです。めちゃくちゃ強いのに自己都合でしか動きません。ハーレムを守る戦いをすると言ってもそれは自己の権威を守るために闘っているので、全体の為に闘っているわけではありません。しゃーなしで闘っているのです。
強さを簡単に定義すると、自己が明朗かどうかです。潜在意識の顕在化、自己肯定感が高い、自己中心的、このような言い方をする場合もあります。ようは自己が自分という人間を明朗に定義している人は強い人間ということです。ハッキリしている人間は強いですが、強さがハッキリしているということは同時に強さと同じくらい弱さもハッキリしているということです。自己が明朗になればなるほど強いと同時に弱いです。
なので【ただ強いだけの人】【我が強い人、自己中な人】は決定的に足りないものがあります。それが陰要素である二元性の愛や全体性です。愛【二元性、一元性】の話をすると長くなるのでしません(笑)
ただ強いだけの人や自己中な人が
『あー忙しい、忙しい。時間が足りない。』
と言っているのをよく聞くと思います。一見すると怠惰には見えません。しかし先ほどのライオンの話を思い出してください。自己都合でならばいくらでも動くのです。陽要素自体が【動】なので動くのは、なんなら得意なぐらい。
これが【全体の為】になった途端、一気に怠惰化します。体調悪くなります(笑)本当に風邪ひきます。
これが強さによる怠惰です。自己がハッキリして強いからこそ、とてつもなく弱いのです。これは強さによる怠惰なのですが、一般的なイメージの【動けない怠惰】もあります。これは陽サイド【月のチャクラの通りが悪い、タマス】の状態といえます。なので同じ怠惰でも色んな見方があるということですね。
あくまでも陽要素なので男女ともにあります。 次回は陰について【優しさと厳格性、激昂】について書いていきたいと思います。
ではまた
(HIROSHIMAストレッチ)
2023年7月11日 17:20





陰と陽 【強さ 優しさ】
だいぶ久しぶりの投稿になります。
ということで今日は陰と陽について話していきたいと思います。東洋思想における陰と陽、聞いたことがある方も多いんじゃないでしょうか。陽サイドと陰サイドでまとめてみると、、、
陽サイド…左、夏、月、猫、男、強さ、個人【我】、怠惰 などなど
陰サイド…右、女、冬、太陽、犬、優しさ、二元性の愛【全体性】、激昂 などなど
があります。意外なのが陽が月で、陰が太陽というところではないでしょうか?しかしこれで合っています。これを説明しだすと長くなるので、また機会があれば説明したいと思いますが、ヨガをやられている方なら左が月のチャクラ、右が太陽のチャクラと習ったことがあると思います。(ラジャス、タマス、サットバという3つのエネルギー)なので左が月、右が太陽というのは受け入れやすいかなと思います。
今日お話ししたいのは強さと優しさについてです。強さは陽サイドで、優しさは陰サイドです。ここで突然の質問をします。間違いはないので直感で選択してみてください。
【愛の反対はなんですか??】 【1.憎しみ】【2.無関心】【3.その他】
1.を選んだ人は愛ある優しい陰サイドの傾向があります。2.を選んだ人は強さのある陽サイドの傾向があります。3.を選んだ人は陽サイドよりの現実思考の傾向があります。※傾向があるだけであってみんな陰要素、陽要素ともに持っています。
実はこの持っている特性で身体の気のめぐりの状態も変わってきます。陽よりの身体、陰よりの身体、陰中の陽、陽中の陰など身体の不調に陥りやすい形もあります。 これは季節、時期の影響も多大に受けます。ストレスにしても自分の身体が何に反応しているのかなどがより理解できるようになってくると対策も打ちやすくなりますが、総じて言えるのは
【呼吸めっちゃ大事】
ってことです。なにかあったときにはまずは呼吸を意識してください。
【力みの無い真ん中の呼吸】
言っていることがわけわからないと思いますがイメージでやってください。(笑)
【力みの無い真ん中の呼吸】
です。呼吸はどのタイプの身体、思考であろうが抜群に効果あります。
困った時には呼吸。試してみてください。
(HIROSHIMAストレッチ)
2023年7月11日 17:20





身体が重い、、、そんな時こそ♪
2023年、私の初めてのブログは【呼吸について】サラッと書いてみようと思います。
みなさん呼吸は意識しないでも行っているはずです。呼吸していないとしたら、、、ケンシロウのあの一言を言わなければなりません(笑)
その呼吸は基本的に肋骨が前後左右上下に動くことで肺が広がり、空気が入って来て酸素と二酸化炭素の交換をしているわけです。
その肋骨の動きをだしているのは下の図にあるように肋骨の間にある筋肉達と【横隔膜】です。
更に大きく息を吸ってみようと思うと首から肩にかけての筋肉も使うんですね!
(下の図の胸鎖乳突筋や斜角筋とかいてある部分です。)
 (生体のしくみ標準テキスト第3版 新しい解剖生理学より抜粋改変しております。)
(生体のしくみ標準テキスト第3版 新しい解剖生理学より抜粋改変しております。)HIROSHIMAストレッチでは身体をリラックスさせるために【深呼吸をしてみましょう!】とお伝えする事が多いですが、その深呼吸一つとっても意識するポイントが変われば上手くリラックスに繋がりません、、、。
先程書いたように思いっきり息を吸う時には首肩の筋肉も働きます。これは人間の構造上仕方ありません。
しかし、過剰に首肩に力を入れてしまうと逆に身体が緊張してしまう可能性もあると考えています。
そこで深呼吸をする際に【身体の中心を意識する】ことを注意点としてお伝えしています。
身体の中心?と思う方は上の図のピンクのラインが自分の身体にあるという事を意識してみて下さい。
ちょうど身体を3Dで考えてみるとピンクのライン上に【気道】があります。
気管などの空気の通り道ですね!
そこに空気をしっかり入れることを意識して深呼吸をしてみる。
そうすると肋骨周りや首肩回りにも少しは力が入るんですが、首肩をメインに使った深呼吸よりも筋肉の緊張度合いの違いに気付けると思います。
お仕事など集中するとどうしても呼吸が止まりがちになりますが、そんな時こそこの【身体の中心を意識した深呼吸】を実践してみて下さい。
身体だけでなく頭もスッキリしてきますよ♪
では、2023年もHIROSHIMAストレッチをよろしくお願い致します。
またねー。
(HIROSHIMAストレッチ)
2023年1月13日 11:42





秋と呼吸の関係について。
どうも、楠本です。
毎年思うことですが、9月から11月中旬にかけて気候の変動が激しいように思います。
朝晩は冷え込んで、日中はめちゃくちゃ暑いみたいな。
身体がその変動に追いつかず、重い、だるい、しんどいなどとにかく思うように使えない。更に喘息っぽくなったり、呼吸が浅くなったりするとの訴えも多いと。
これはなんでかな?なんて少し考えてみました。
鍼灸師でもありますので、東洋医学に何かヒントあるんじゃない?ってことで今日のタイトルです。
東洋医学の古い書物にはそれぞれの季節に対する養生法を記載している文章があります。
ホントざっくりいうと
『その季節の過ごし方間違うと次の季節の時に身体に不調がでますよ。
なのでそれぞれの季節に合わせた過ごし方しましょうね!』
ってことが書いてます(笑)
更にそれぞれの季節に身体の機能が割り当てられています。
例えば春→肝 秋→肺
みたいなことです。
秋は肺と関係がある季節なんですね!
肺と聞くと呼吸に関係しそうですよね。そうなんです。関係大ありです。
秋になると喘息っぽくなったり、呼吸が浅くなったりしやすいのはこのように気候も関係していると思います。

しかも昔の人は秋の前の季節の夏を上手に過ごせなかったら秋に肺の機能が低下して不調になりますよと言っています。
つまり、今何かしら身体の不調がある方は夏に引きこもったり、うまくストレスなどを発散できなかった、寝る時間や起きる時間が季節にあってなかった人ですと。
じゃあもう間に合わんじゃん!ってことになりますが、そういうことはありません。
秋の養生法を守れば肺の機能も少しずつ戻り、冬の不調も防ぐことができます。
一つ、早寝早起きをする。(にわとりと同じぐらい早起き笑)
一つ、精神を引き締めて、気持ちを穏やかに過ごす。
一つ、活発な活動はやり過ぎないようにする。
この3つを心がけることが大切といわれています。
*正確な訳ではなく、知ってる人は批判したくなるかもしれませんが、ご容赦を。
今からでもこの3つを意識しながら生活してみましょう!
きっとカラダの変化を感じれます!
今日はここまで。
ありがとうございました。
(HIROSHIMAストレッチ)
2022年11月 4日 18:31





臀筋:トレーニング編
トレーニングって筋肉を収縮させることですよね。つまり起始と停止を近づける。
ここで、解剖学編でやったことをもう一度思い出して頂きたい!臀筋の作用はなんでしたか?今回のトレーニングで動かしたところは【股関節】ですよ!
トレーニング(1)
1)四つ這いの姿勢で準備
2)骨盤の位置が変わらないように膝を開く(上げる)×10(2セット)
 ※便宜上、膝を開くと書いてありますが、やりたいことは【股関節外転・外旋】
※便宜上、膝を開くと書いてありますが、やりたいことは【股関節外転・外旋】※NGポーズに注意!
→しんどくなってきたら頭が下がりやすくなります。
目線は手の平の先を見て、顎が胸に付かないように!
トレーニング(2)
1)うつ伏せで準備
2)手の平を重ね、その上におでこを乗せる
3)足の幅は骨盤より少し広めに開き、踵同士をくっ付け膝を曲げる
※骨盤後傾位で恥骨を床につける
4)恥骨はなるだけ浮かないように、膝を上げる×8

トレーニング(2)は少し難しいかもしれません。そしてシンプルにキツイ!(笑)
イメージは骨盤は固定したまま(=恥骨を床につけたまま)、大腿骨を上げる!腰が痛くなったら間違いだと思ってください。
トレーニング(3)
1)横向きで準備(=膝は骨盤と同じライン)
2)骨盤が動かないように膝を開く(=外旋)×10(2セット)

トレーニング(4)
1)トレーニング(3)と同じ姿勢で準備
2)上にある足を伸ばし、【ゆっくり】足をあげる(=外転)
※勢いにならないこと!あげるときよりもゆっくり足を下ろすことでより鍛えられますよ。
※上にある手を臀筋に当てることでしっかり臀筋を使えているかをチェック!

トレーニング(3)(4)はいかにゆっくり動かすか、がポイントになります!上にある手で、しっかり臀筋の収縮を感じながら、トレーニングしてみてください!
さて、いかがでしたか。全編6編という、思わん長くなった臀筋シリーズ!
今までやってなかったものはぜひぜひチャレンジしてみてくださいね。
(HIROSHIMAストレッチ)
2022年10月 6日 16:59





臀筋:ストレッチ編
ストレッチ(1)
1)足を伸ばして準備
※骨盤が寝ないように注意する=坐骨はしっかり床を突き刺し、上前腸骨棘は正面を向くように
2)ストレッチする側(写真だと左)の足をクロスさせる
※1:このとき太ももとお腹をくっ付け、更に骨盤を立たせる
※2:足をクロスさせるのが難しい人はクロスせず、膝を曲げて立たせるだけでOK
3)2)で作った骨盤の感覚をキープしたまま、伸ばしてる足側の(右)肘を立ててる(左)膝に引っ掛け、立ててる足と同じ方向(左)にツイストする
※立ててる側のお尻が浮きやすいので浮かないようにする(画像参照)

ストレッチ(2)
1)両方の膝を重ねるようにして準備
2)骨盤を立てたまま、おへそ(か上前腸骨棘)が下の膝にくっ付くイメージで骨盤を前に倒す(骨盤前傾)
※ただ背中が丸まるだけでは臀筋は伸びません!
【更に負荷を高めたい人】
3)2)の状態を作れた上で上体をしっかり遠くに倒す
※1:上にある膝よりも遠くのところにおでこが付くように
※2:繰り返しになりますがただ背中を丸くしてもダメですよ。臀筋の付着部を思い出してください。骨盤から倒す理由はここにあります!

ストレッチ(3)
1)足は骨盤幅に開き軽く膝を曲げて準備(=体操座り)
2)ストレッチする側(写真だと左)の足を内側に倒す
3)倒した足の上に反対足を乗せる=重みで臀筋が伸びてくるのを感じれたらOK

ストレッチ(4)
1)ストレッチする側の足(右)をあぐらをかくような形で準備し、反対側は後ろに伸ばす
2)余裕がある人は上体を前に倒す
※骨盤は真っ直ぐ前向きで、上前腸骨棘の高さが変わらないようにするのがポイント。前に置いてある足に体重がかかりやすいので、両方の坐骨に均等に体重がかかるように!

上体を起こすか、倒すかだけで負荷は違います。
またストレッチする足(前側)の角度によっても伸び感はかなり変わります!わたしも正直レベル4はキツいです、!(笑)
負荷はチョイスして自分が一番痛気持ちいいと感じるラインでストレッチしましょう!
ちなみにストレッチ(4)は腸腰筋のストレッチ(2022/06/06)の流れでできるのでオススメですよ。
骨盤に付着する筋肉の前側も後ろ側もしっかりストレッチです!
さていかがでしたでしょうか?
お尻はそんなに使ってる感じがしないからストレッチするのを忘れがちになります。
座る時間が長いよって方。もれなくお尻はカチカチにかたまってますよ~!
これなら出来そうかも?というのを見つけて伸ばしてあげてくださいね。
(HIROSHIMAストレッチ)
2022年9月17日 11:14





<<前のページへ|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|次のページへ>>
100件以降の記事はアーカイブからご覧いただけます。