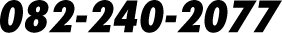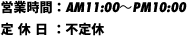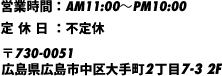カテゴリ
月別 アーカイブ
- 2024年5月 (1)
- 2023年11月 (1)
- 2023年10月 (3)
- 2023年9月 (6)
- 2023年8月 (8)
- 2023年7月 (7)
- 2023年1月 (1)
- 2022年11月 (1)
- 2022年10月 (1)
- 2022年9月 (2)
- 2022年7月 (6)
- 2022年6月 (3)
- 2022年5月 (4)
- 2022年3月 (5)
- 2022年2月 (6)
- 2022年1月 (4)
- 2021年11月 (2)
- 2021年10月 (4)
- 2021年9月 (2)
- 2021年8月 (2)
- 2021年5月 (1)
- 2021年4月 (1)
- 2021年3月 (4)
- 2021年1月 (2)
- 2020年11月 (1)
- 2020年10月 (1)
- 2020年8月 (2)
- 2020年4月 (3)
- 2020年3月 (1)
- 2020年2月 (4)
- 2020年1月 (3)
- 2019年12月 (7)
- 2019年11月 (2)
- 2019年10月 (3)
- 2019年9月 (2)
- 2019年8月 (6)
- 2019年7月 (16)
- 2019年6月 (21)
- 2019年5月 (22)
- 2019年4月 (7)
- 2019年3月 (3)
- 2019年2月 (7)
- 2019年1月 (4)
- 2018年12月 (6)
- 2018年11月 (8)
- 2018年10月 (3)
- 2018年9月 (12)
- 2018年8月 (6)
- 2018年7月 (3)
- 2018年6月 (8)
- 2018年5月 (10)
- 2018年4月 (3)
- 2018年3月 (2)
- 2018年2月 (1)
- 2018年1月 (3)
- 2017年12月 (4)
- 2017年11月 (4)
- 2017年10月 (2)
- 2017年9月 (4)
- 2017年8月 (5)
- 2017年7月 (1)
- 2017年3月 (1)
最近のエントリー
ブログ 7ページ目
ストレッチチャレンジ経過報告~48日目~
どうも、楠本です。
今日はストレッチチャレンジの経過報告とカラダの柔軟性獲得に向けての戦略をお伝えしようと思います。
まずは48日経過した私の長座体前屈をご覧ください(笑)
 ちょっと見にくいですが、だいぶカラダが曲がるようになってきました♪
ちょっと見にくいですが、だいぶカラダが曲がるようになってきました♪柔軟性を出していくときに重要なのはもちろん、筋肉が緩んでちゃんと伸びること!これは大前提です。
写真のように前屈する場合、黄色で示した背中、腰、お尻、太ももの裏、ふくらはぎなどは
しっかりビヨーっと伸びる必要がありますよね♪
ここが伸びなければ身体は折りたためないわけです(笑)
なので一生懸命に太ももの裏、腰や背中のストレッチをするわけです。
ただ、もう1つ重要な事が有ります。
それは青色の線で示した部分です。これは何を表しているかと言うとカラダを折りたたむときに働いている筋肉達です。
つまり、股関節を曲げる筋肉達。
この筋肉達が働かないとカラダを折りたたむことができません。
いくらカラダの後ろ側が伸びるようになっても、カラダの前側の筋肉がうまく縮めないと深く前屈出来ないわけです。
今回は前屈を例に出しましたが、カラダのどこでも同じです。
今日のまとめはこちら
『柔軟性獲得にはしっかり伸びるところと、しっかり縮むところのバランスが大事!』
ストレッチとトレーニングの両方を頑張って、快適なカラダを手に入れましょう♪
おカラダのご相談はHIROSHIMAストレッチまで!お待ちしてまーす♪
くっすんがお送りしました(笑)では、またね~♪
(HIROSHIMAストレッチ)
2021年11月 4日 18:46





お尻に近い腰痛改善のストレッチ♪
どうも、楠本です。
無理は禁物ということです。しっかりとセルフストレッチ等してるんですが、回復が追い付いてないのかもしれません。
今日は前回に引き続き、腰痛改善のストレッチ第2弾。
前回はハムストリングスのストレッチでしたが、今回は腰の下、お尻に近い所の筋肉を伸ばすストレッチを一つご紹介します。
*腰椎椎間板ヘルニアや脊柱管狭窄症などがある方は無理に行わないように注意してください。
次にお見せする写真のような体勢を取った時、激痛や足にしびれや痛みが出る場合は行わないようにしましょう!無理は禁物です。
では写真でご紹介しま~す。
まずは体勢作り!ストレッチする方を上にした横向きに寝ます。写真のように足をセットします。
 次は上の足のセッティングです!両手を膝の裏に回して抱えます。このとき膝の前側から抱えないということがポイントです。必ず膝裏からですよ~!
次は上の足のセッティングです!両手を膝の裏に回して抱えます。このとき膝の前側から抱えないということがポイントです。必ず膝裏からですよ~!
この体勢が取れたら、いよいよ伸ばしていきます。赤丸で示したように上にしている膝と肩がくっつつ様に足を引き寄せます。この時に肩が膝を迎えに行かないようにしましょう。
そうするとオレンジのライン、腰の下からお尻にかけてがじわっと伸びてきます。
 強い伸びている感じはしませんが、この体勢で10秒キープです。
強い伸びている感じはしませんが、この体勢で10秒キープです。これは筋肉のストレッチだけでなく、腰椎や骨盤の動きを改善するストレッチにもなります。
無理のない範囲で10秒を5セット行います。
カラダを調子良くしておくには、日々のセルフストレッチもとても大切です。
実際に私自身、太ももの裏のストレッチを毎日行うことで腰痛を感じなくなっています。
みなさんのストレッチの参考にしてもらえると幸いです。
インスタグラム『hiroshimastretch』では365日ストレッチチャレンジとストレッチ方法などもアップしています。
そちらも是非、覗いて頂けると嬉しいです♪
https://www.instagram.com/hiroshimastretch
では、今日はこの辺で失礼します!
またね~♪
(HIROSHIMAストレッチ)
2021年10月 8日 11:55





硬いハムストリングスの改善方法!
どうも、楠本です。
昨日に引き続き、またハムストリングスです(笑)
今日は硬いハムストリングスのの改善方法をお伝えしようと思います。うん、セルフストレッチの方法ですな。
筋肉の反射を使った方法になります。また、仰向けで寝ないとできないのでお家で、ジムで寝転べるところでやってみましょう♪
以下の方法はインスタグラムでも公開している方法となります。
まず、仰向けで寝ます。
次に、膝を曲げた状態で膝裏に手をまわして、手で引っ張って脚を自分の胸の方へ近づけます。
そして、膝を伸ばせるだけ伸ばします。
 そうすると太もも裏がピーンと張ってくると思います。
そうすると太もも裏がピーンと張ってくると思います。太もも裏の痛みが我慢できる程度の所まで膝を曲げます。恐らく5°ぐらい下ろすので丁度良いかと思います。
ここからがストレッチ!
太ももの裏に力を入れて脚を下ろすようにします。(青矢印)
抱えている手は脚が下りないように頑張って抵抗します。(赤矢印)
*入れる力の程度は1割ぐらいで大丈夫です。
この状態で10秒間キープします。
10秒経ったら一回脱力し、最初に戻るって感じです。

写真を参考にやってみてください。
私自身は毎日5セット行っています。
この方法だと筋肉に無理なくストレッチすることができるので効果的です。
う~ん、イマイチ方法が分からんという方は一度HIROSIMAストレッチに来てください(笑)
この方法だけでなく、身体に合わせたセルフストレッチもお伝えしていますので♪
これでハムストリングスの硬さを取っていけば腰痛も改善しますね!
じゃあ今日はここまで。
また、お会いしましょう♪
(HIROSHIMAストレッチ)
2021年10月 3日 12:58





硬いハムストリングスのデメリット.
前回のブログで『太もも裏が硬いと腰痛になるかも!?』という話をしました。
なので今日はもう少しハムストリングスについて突っ込んだ話をしたいと思います。
まず、ハムストリングスって何ってところから。
太もも裏にある大腿二頭筋、半腱様筋、半膜様筋の3つの筋を合わせてハムストリングスと言います。
こんな感じ↓
 (画像はアナトミートレイン~徒手運動療法のための筋筋膜経線~第2版より抜粋)
(画像はアナトミートレイン~徒手運動療法のための筋筋膜経線~第2版より抜粋)図の赤丸と青丸の間にある濃い紫色の筋肉がハムストリングス。
外側が大腿二頭筋、内側が半腱様筋、半膜様筋。
ハムストリングスは骨盤の坐骨結節から始まります。(起始と書いてある赤丸部分)
坐骨結節は椅子に座った時に当たる骨の部分。
ハムストリングスの終わりは膝を超えて内側と外側。
なのでこの筋肉の作用は股関節の伸展と膝の屈曲。
つまり、足全体を後ろに引く時や歩くときの蹴り出しの時に働きます。
更に膝を曲げるための筋肉でもあります。
このハムストリングス、前述の通り骨盤の下に付きますので硬くなると、、、。
何だか骨盤の歪みを起こしそうですよね?
はい、その通り。
骨盤が後ろに倒れることにより腰・背中が丸まる、いわゆる『猫背』にも繋がります。
更に前屈する時に骨盤の動きを制限するので腰の骨(腰椎)だけで動くようになり、『腰痛』の原因になります。
更に更に、仙腸関節にある靱帯の緊張を高めるのでこれも『腰痛』に繋がります。
ハムストリングスが硬いだけでも色んな不調を生み出します。
特に今の時期は硬くなりやすい傾向がありそうなので注意してください!
ストレッチの方法はインスタグラム『hiroshimastretch』で公開中。
私自身のハムストリングスも柔らかくなってますので是非参考にしてください!
最近ハムストリングスにこだわり過ぎてるんじゃないか説が浮上している、楠本がお送りしました(笑)
またね~♪
(HIROSHIMAストレッチ)
2021年10月 2日 16:52





腰の下の方~お尻にかけて痛くないですか!?
どうも、楠本です。
今日はカラダについて書いていこうと思います。
最近、腰痛くないですか!?
うんうん、痛いと思ったそこのアナタ!もしかしたらそれは『裏もも』と『お尻』の硬さが原因かもしれません。
腰を動かす時、前屈でも、後ろに反らすのも、捻じるのも全て骨盤や股関節の動きがないとしっかりと動きません。

前屈の場合はこんな感じですねー。手が床に届いてないのはご愛嬌(笑)
腰の骨(腰椎といいます)の可動域は狭いので、股関節や骨盤の動きの関与の方が大きいと言えますね!
ここから何が言いたいかと言うと、今骨盤の後ろ側、仙骨と呼ばれるお尻なのか腰なのか判断付きにくい場所の痛みというのは意外と
『太ももの裏の硬さ』、『お尻の筋肉(股関節を外に捻じる筋肉)の硬さ』
が関わっていますよーという事。この2つが硬くなることで骨盤の前傾という動作が妨げられます。
さらに今の時期は特に起こりやすい腰痛な気がします。
あっ、自分かもと思った方は一度HIROSIMAストレッチへご来店ください。
もしかしたら別の要因かもしれませんので。
スタッフ一同、お待ちしております♪
太もも裏のストレッチの方法はインスタグラム『hiroshimastretch』で公開中です。
ストレッチチャレンジ1日目と3日目を参考にしてください。
ついでにフォローなんかして頂けると嬉しいです。
ストレッチの方法なども写真を交えて今後もアップしていく予定です♪
よろしくお願い致します。
(HIROSHIMAストレッチ)
2021年10月 1日 17:05





継続のコツなる物を発見!?

冒頭でも触れたように、2週間前からランニングを始めました。
小さい頃から走ることは大好きで、高校では陸上部に所属しておりました。
今年34歳になり、意識的に動かないとカラダがたるんでくるようになりました。
自分自身はこの34歳から体力が一気に落ちてしまう、更に健康管理の年に当たっています。
このまま体力が落ちていくのを待つのはシャクだなと思い、
いっそのこと体力作りをして現状打破してみようってなったわけです。
ハマらないものは、3日やったら飽きる。
そんな性分の私が、何とかして継続できる方法は無いかと頭を捻りました。
それが、
1,記録をつける
2,SNSに上げる
3,徐々に距離を伸ばす
この3点を絞り出し、実践しようと考えました。
今はめちゃくちゃ便利ですね♪アディ〇ス、ナ〇キなどのスポーツメーカーがランニング記録アプリを出してます。
ちゃんと距離やタイム、消費カロリー、1キロ当たりのタイム何かも出てきます。
これは良いと思って早速ダウンロードして、スマホを装着してランニング!
音楽も聴けるし、楽しくランニングできます。
こうして1つ目はクリア!
SNSにはこのランニング記録をそのまま上げてます。
そうすることで、皆に応援してもらってる感覚になります!
そして今日もインスタにアップしようと思えるんですね。何か行動を起こすときにはSNSにて宣言してみるってのも手だと思いました。
3つ目はいきなり無理しないってことです。
セルフストレッチも同様で、最初から毎日30分しようと思うととても大変です。
少しずつ時間を、回数を増やせばいいんです。
今日はこれぐらいって感じから始めるのはとても大切な事です。
『し続ける』って大変だけど、とても大事です。
是非、何かをしようと思う時、いきなりステーキ。じゃなくて、いきなりエンジンふかすのではなく、アイドリングしてゆっくり始めるってことを意識してみてください。
良かったらインスタグラムも見てください(笑)
では、また。
(HIROSHIMAストレッチ)
2021年9月30日 16:32





365日 ストレッチチャレンジ♪
今日は1週間ほど前から始めたストレッチチャレンジについてお話しようと思います。
ストレッチって毎日続けないといけないんですか!?
毎日5分ぐらいの時間のストレッチで効果あるんですか!?
そんな疑問に自分のカラダを使ってお答えしようと思い、始めました。
結論から言うと、ストレッチはトレーニングと同じで毎日続けないとダメです。
筋肉(骨格筋)は筋節(サルコメア)というものがいくつも繋がって長い筋繊維になっています。
まぁ竹をイメージしてください。いくつもの節が繋がって長い竹になってますよね?そんな節が筋肉にもあるんです!
そして、ストレッチを続けることにより、その節の数が増えて筋肉が伸びやすくなるという報告があります

ということでストレッチは続けないといけないということになりますね!
1日30分も1時間もストレッチする時間がとれる人は少数でしょうから、一日5分で行えるストレッチでどう変化するか。
これをやってみようと思います

詳細はHIROSHIMAストレッチのインスタグラムにアップしていってますので、
是非覗いて頂けると嬉しいです。
では、また~。
(HIROSHIMAストレッチ)
2021年9月26日 11:22





知っているようで知らない筋肉
お久しぶりの投稿となりました。
今日は筋肉について深堀っていきたいと思います。途中混乱するかもですがついてきてください!
まず初めに筋肉の種類について話すと、骨に付着し関節を動かしたりする意識的に動かすことのできる(随意筋)骨格筋とよばれる筋と血管や臓器などの壁にある平滑筋とよばれる筋と心臓にしかない心筋とよばれる筋肉の分類があります。平滑筋と心筋は骨格筋とは異なり意識的に動かすことのできない(不随筋)と呼ばれます。
まず写真を見てください!
 これは骨格筋の組織の構造になりますが筋肉がさらに細かく束のようになっています。
これは骨格筋の組織の構造になりますが筋肉がさらに細かく束のようになっています。また、それを覆う膜もありそれらを写真右から筋外膜、筋周膜、筋内膜と呼びます。
実は筋膜にも構造はあるんですがここでは割愛します。
今度もう一度先程の写真に戻ってもらうと筋原線維と呼ばれるものがありますよね。これもまたさらに細かく見ることができてミオシンフィラメントとアクチンフィラメントというタンパク質からなります。
この辺で頭が混乱状態の人が多いかと思いますのでまたまた写真を!
 写真のようにミオシンの間をアクチンが滑り込むようにして筋収縮が起こります。
写真のようにミオシンの間をアクチンが滑り込むようにして筋収縮が起こります。またこのZ帯とZ帯というのがありますがこれを筋節と言い別の呼び方でサルコメアと言います。
ミオシンの間にアクチンが滑り込むという事は、、、
筋収縮する時、Z帯からZ帯の幅は短くなるつまりサルコメアが短くなるということです。
これらを簡単にまとめるとストレッチをするという事は伸ばすことで脳が縮めの命令を出すのでそれによって筋肉が収縮をし筋肉が弛むということです。
でもこれは極端に言ってるのでこれが全ての意味ではありませんので、、、
ストレッチが大事とは言いますが解剖学的にどういうことが身体で起きているのかを知るとまた更に効率的かつ効果的にストレッチが出来るのかもしれませんね。
(HIROSHIMAストレッチ)
2021年8月17日 19:28





お盆休みのお知らせ
暑い日が続いておりますが、皆様、体調崩されていませんか?
年齢が上がるほどに身体の水分は不足しがちです。こまめな水分補給を心がけましょう♪
直前で大変申し訳ございませんが、お盆休みのお知らせです。
誠に勝手ながら【8月13日(金)~15日(日)】の3日間、お休みを頂きます。
8月16日(月)からは通常通り営業いたします。
ご迷惑をお掛け致しますが、何卒ご了承くださいますようよろしくお願い申し上げます。
(HIROSHIMAストレッチ)
2021年8月12日 12:40





梨状筋
今回は梨状筋についてお話します。
まず梨状筋は仙骨から大腿骨の大転子にかけて付着する筋肉で、
深層外旋六筋という股関節を安定させる筋肉の一つとして働いています。
この筋肉は股関節の動きの中でも複雑で、本来は股関節の外旋で働きますが、
股関節の屈曲90°(座った状態)では内旋に働く作用もあります。
股関節を内旋して臀部が痛む場合は股関節の外旋筋群が硬くなっていて、その下にある
坐骨神経が圧迫されている可能性があります。
これが梨状筋症候群といっていわゆる坐骨神経痛です。
予防としてはストレッチが重要にはなるのですが、梨状筋はかなり深い所の筋肉なので
狙って鍛えたりストレッチすることは難しいです。
なので普段から股関節のストレッチを行っていくことで予防ができます。
ここが上手く使えてくると、歩行の補助であったり、股関節の安定をしてくれる筋肉になるので
股関節周りが疲れにくくなります。
みなさんも股関節意識しながらストレッチ頑張ってみて下さい!!
もっと詳しくストレッチが知りたい又は興味を持った方は
HIROSHIMAストレッチまでお待ちしております。
(HIROSHIMAストレッチ)
2021年5月 9日 12:19





<<前のページへ|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|次のページへ>>
100件以降の記事はアーカイブからご覧いただけます。